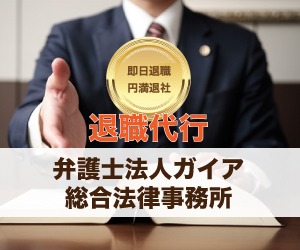今、なぜ「退職代行」を選ぶ人が増えているのか
「辞めたいけれど会社に言い出せない」――そんな悩みを抱える若手は少なくありません。
上司への報告、引き止め、退職後のトラブルへの恐怖。これらが理由で、辞めたくても辞められない人も多いでしょう。
しかし現在、日本は 就職売り手市場 の局面にあります。
多くの企業が人材確保に苦心しており、若手・未経験者にも門戸を開く求人が増加しています。
こうした追い風のなか、退職代行サービス を賢く活用することで、精神的・物理的コストを抑えながら、次のキャリアにスムーズに移行できる可能性が高まります。
この記事では、20〜30代を主な読者対象とし、統計データ・公的資料を交えつつ、退職代行を使うメリット・注意点・活用戦略を詳細に解説します。さらに、今注目すべき業界モデルとして 航空業界・地上支援(グラウンドハンドリング/運航支援) の現状と将来性も取り上げます。

退職代行の実態と統計データで見る広がり
1-1. 利用率・認知度の現状
- マイナビの調査によると、「直近1年間に転職した人」のうち 16.6% が退職代行を利用したと回答しています。 マイナビキャリアリサーチLab | 働くの明日を考える
- 年代別に見ると、20代では 18.6% が利用経験ありと答えており、若年層での利用率が最も高い傾向にあります。 マイナビキャリアリサーチLab | 働くの明日を考える
- 一方で、エン・ジャパンの調査では、退職代行サービスの 認知度は72% に達しており、20代では 83%、30代では 78% が「サービスを知っている」と回答しています。 エン・ジャパン(en Japan)
- ただし、「実際に利用したことがある人」は全体で 2%程度 にとどまるという調査もあります。 エン・ジャパン(en Japan)
- また、FNN の調査では、実際に利用した人は約10%とする意見もありつつ、退職代行を検討したことがある人は26% に上るという結果も報じられています。 FNNプライムオンライン
- TSR(東京商工リサーチ)の企業調査では、従業員が「退職代行」を使った経験のある企業は 全体の約9.3%。大企業では 18.4% にのぼるとの報告もあります。 TSR-ネット
これらを総合すると、退職代行はまだ「全員が使うもの」ではないものの、若手層を中心に確実に広がりつつあるサービスであることがわかります。
1-2. 利用者属性・傾向
- TSR の調査によれば、退職代行利用者のうち 60.8% が20代、26.9% が30代 というデータがあります。 TSR-ネット
- さらに、利用が報じられた企業数を見ても、退職代行業者から連絡を受けた経験のある企業割合は 約9.3%、大企業では 18.4% に達するとの報告があります。 TSR-ネット
- 退職代行業者「モームリ」の統計では、累計利用者数 15,934名、複数回利用された企業 1,466社(全体の9.2%)に上るというデータもあります。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
- また、2024年度の新卒社員で退職代行を利用した人数・職種も公表されており、サービス業・営業・医療関連など幅広い分野で利用があることが示されています。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
- 利用頻度が高い企業もあり、モームリへの退職代行依頼が 103回 に及ぶ企業もあるという報告があります。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
就職売り手市場の構造と強みを理解する
なぜ今「転職がチャンス」なのか、その背景を整理しておきましょう。
2-1. 少子高齢化と労働力人口の減少
日本は少子高齢化が進み、労働力人口そのものが減少傾向にあります。この流れは長期的な構造変化であり、企業は人を確保し続けなければ成り立たない状況にあります。
特に地方や中小企業では、若い人材の確保がますます困難になっており、「人材を取りに行く」構図が常態化しつつあります。
2-2. ポストコロナ需要の回復と拡大
新型コロナウイルスの影響で停滞していた、観光・物流・航空・飲食産業などが回復基調にあります
中でも、航空業界や空港関連の需要は国内外の旅行回復とともに再び強まってきています。これにより、関連業界での採用ニーズが底上げされています。
2-3. 働き手の価値観変化と待遇重視志向
働く人の意識も変化しています。「時間よりも働きやすさ」「ストレスの軽減」「ライフバランス」が重視されるようになってきました。こうした価値観の変化を反映して、企業も待遇改善・フレキシブルな働き方を打ち出す必要性に迫られています。
2-4. 転職マッチング技術の進化
転職プラットフォーム・スカウト型求人・オンライン面接などの進化により、求職者側が企業情報を手軽に入手できるようになりました。
特に「在職中転職」が増えており、現職を続けながら次を探す人が増加しているという分析もあります。arXiv の研究では、日本の求人マッチング効率が上昇傾向にあり、プラットフォームを介したマッチング弾力性が高まっているという報告もあります。 arXiv
これらの要素が複合して、「企業が人材を奪い合う」状況、すなわち就職売り手市場が形成されているのです。
退職代行を使うメリット ― “損をしない、むしろ有利になる”理由
3-1. 精神的・心理的負荷の軽減
最も訴求力のあるメリットがこれです。退職の意思をどう伝えるか、納得する理由をどう説明するか、交渉をどう乗り切るか――こうした心理的負荷は非常に大きいもの。
退職代行を使えば、そのストレスをプロに任せられるため、読者自身は次のステップに備える心の余裕が生まれます。
3-2. スピード対応・即日出社不要の可能性
法律上、退職の意思表示は2週間前でよいと解されるケースがありますが、実際には「即日出社不要」扱いとなることも少なくありません。
退職代行業者が会社とのやり取りを代行することで、出社せずに手続きが完了する場合があり、そのスピード感が大きな利点になります。
3-3. 権利・条件交渉の後押し
有給休暇の消化、未払い残業代の請求、最終給与清算、社会保険手続きなど、自分一人では言い出しにくい交渉を代行してくれる業者もあります。
「退職代行だから交渉もできる」という誤解をしてはいけませんが、補助的に動いてくれるタイプを選ぶことで安心度は高まります。
3-4. 転職準備に集中できる時間確保
退職交渉・やり取りに時間を取られないため、その分を履歴書・職務経歴書の準備、面接対策、業界研究やスキルアップに充てられます。時間を無駄にしないという点は、売り手市場での武器になります。
3-5. 選択肢をじっくり選べる余裕
退職のタイミングを自分でコントロールでき、焦らずに複数の求人を比較したうえで選べるようになります。売り手市場だからこそ、「いつ辞めるか」がキャリア戦略上、非常に重要です。
3-6. 辞めづらさという心理的障壁の打破
「会社に迷惑をかけるかも」「辞めたら後悔するかも」という罪悪感、あるいは辞めづらさを感じる心理的な障壁を打ち破るための選択肢として、退職代行の存在自体が救いになることがあります。
少しオーバーかもしれませんが、離婚の際に、弁護士に入ってもらった方が解決に結びやすいケースと似ていますよね。

注意点とリスク管理 ― 安全に使うためのガイドライン
4-1. 悪質業者・グレー業者の見分け方
- 料金が不透明・成功報酬を謳っているが条件が曖昧
- 法務能力を誇張(「訴訟も対応」など)しているが実態が不明
- 口コミや実績が乏しい/検索しても信頼情報が出てこない
- 対応内容が「辞表を伝えるだけ」「形式的な代行のみ」の範囲であるという説明がない
こうした業者には注意し、契約前に見積もり・契約書を必ず確認しましょう。
4-2. 弁護士対応型・弁護士監修型の安心感
退職・賃金未払い・訴訟リスクの可能性を含む場合は、弁護士対応型や弁護士監修型の代行サービスを選ぶことを強くおすすめします。法的裏付けがあると、会社側とのやり取りでの交渉力も違います。
4-3. 短期間離職・多重代行の印象リスク
あまりにも短期の離職が続く、退職代行を何度も使う、という履歴は、採用側に「安易に辞める可能性が高い」と見なされるリスクがあります。履歴書・面接での理由説明は慎重に構築すべきです。
4-4. 引き継ぎ不備や社内調整未処理リスク
代行にすべて任せすぎると、引き継ぎ資料が不備になる、社内混乱を招くなどのリスクがあります。特に組織的・技術的に重要なポジションであれば、最低限の整理・説明書きを残しておくべきです。
4-5. 非弁護士対応の法律的限界
非弁護士が退職代行を行う際、労働者本人への「意思表示伝達」範囲に収めなければ、弁護士法などの法的リスクを指摘される可能性もあります。業者選定時には、その点の説明責任や透明性を確認することが不可欠です。
実践戦略 ― 退職代行を“使いこなす”ためのステップ
ステップ 1:目指す業界・職種を先に絞る
まず自分がやりたい業界・職種を絞り、選択肢を持っておくことが重要です。例えば、IT、物流、介護・医療、航空関連(地上支援)など。複数候補をリストアップしておきましょう。
ステップ 2:在職中に情報収集と準備
転職サイト、スカウト型求人、業界ニュース、知人ネットワークなどを使って情報を集めておく。時間が限られても、複数案件をウォッチしておく態勢を整えましょう。
ステップ 3:退職代行を使うタイミングを見極める
- 精神的・健康面に不調が出てきている
- 職場環境が耐え難いレベルで悪化している
- 転職先の候補が絞れてきている
こうしたタイミングで依頼を検討するのが最適です。
ステップ 4:事前準備をしっかり行う
- 雇用契約書・就業規則・給与明細・過去の勤怠記録などを手元に揃える
- 引き継ぎ資料・業務内容整理は可能な範囲で準備
- 代行業者と見積もり・契約内容を明確にして、代行範囲を確認する
- 私物整理・メールや資料のバックアップを事前に済ませておく
ステップ 5:転職活動とスキルアップを同時進行
退職代行を依頼している間も、履歴書添削・面接対策・業界研究・技術スキル強化などを進めておきましょう。特に目指す業界に関連するスキルを養うことが、転職成功率を高めます。
ステップ 6:複数オファーを持つ・条件交渉する
売り手市場の強みを生かし、複数オファーがあれば条件交渉が可能です。勤務地・給与・休日・福利厚生など、妥協点を決めたうえで交渉することをおすすめします。
航空業界 地上支援業務(グランドハンドリング/運航支援)という選択肢
Beyond the Horizonでは、転職先のモデルとして、現在非常に需要ギャップが大きく、やりがいと将来性も兼ね備えた 航空業界の地上支援(運航支援/グランドハンドリング) を紹介します。
6-1. 航空業界・空港業務の需要回復と課題
- コロナ後、国内線旅客数はほぼ回復、国際線もインバウンド回復を追い風に回復傾向にあります。 国土交通省
- 一方、空港業務(グラハン/保安検査など)は、労働力人口減少や人手確保難という構造的課題を抱えており、DX(デジタル化)・自動化推進による負荷軽減が求められています。 国土交通省
- 国交省(国土交通省)は、空港業務の持続的発展に向け、「人材確保」「DX化・GX化」を軸とした検討会を設置しており、制度的な後押しも始まっています。 Jwing
- グランドハンドリング(地上支援)業務に関しては、地方空港も含めて慢性的な人手不足が指摘されており、特定技能外国人の受け入れや待遇改善が議論されています。 さむらい行政書士法人
- 例えば、グランドハンドリング会社や空港運営者は、空港ごとにワーキンググループ(WG)を立てて人材確保・業務改善を進めており、2023年時点で 48空港が WG を設置、外国人材活用も拡大しており、全国で外国人従業員数は約5.4倍に拡大したとの報告もあります。 Jwing
- また、空港業務における人件費引き上げ・契約見直しも議論されており、賃上げや待遇改善のインセンティブも動き始めています。 tjnet.co.jp

6-2. 地上支援/運航支援スタッフの主な業務と役割
地上支援スタッフ(運航支援・グラハン業務)には、次のような業務が含まれます:
- 航空機地上走行支援(タキシング誘導など)
- 手荷物・貨物取扱、搭降載作業補助
- 航空機内外清掃補助業務
- 運航乗務員(パイロットなど)との情報調整・運航前調整
- 天候・航空管制情報の確認・伝達
- 出発・到着進行管理・運航スケジュール調整
- 安全管理・トラブル対応支援
これらは表には見えにくい仕事ですが、飛行機を無事に運航させる「縁の下の力持ち」として大きな責任と誇りを持てる仕事です。
例えば、ジェットスターの採用ページなどを見ると、業務内容や採用状況も分かります。
https://career-jp.jetstar.com/our-culture/
6-3. 未経験参入可能性・キャリアパス
- 多くの空港会社・地上支援会社は、未経験者・第二新卒を対象に採用を行っており、研修制度を設けていることが一般的です。教育も一般的な業務に比較し、丁寧に実施されると思います。
- 特に地方空港や地方路線拡充が進む地域では、採用ハードルが比較的低くなる傾向があります。
- 将来的なキャリアパスとしては、運航企画・安全管理・訓練担当・空港運営・国際線運航支援などへのステップアップもあります。
- 航空関連業務と言っても多岐に渡り、その時の自分を見ながら職種を選び、その経験を次につなげていくことができる素晴らしい業界だと私は思います。
6-4. やりがい・将来性・安定性
- 航空需要回復の中、地上支援業務はインフラ役割を担う“不可欠な仕事”です。
- 制度整備と待遇改善の流れも見え始めており、業界全体として人材確保・定着に本腰を入れてきています。
- また、DX・自動化技術導入が進む中で、より効率化された付加価値の高い業務も増加することが期待されます。 国土交通省
- さらに、国交省・防衛省は、退職自衛官の航空業界再就職支援を含む協力体制を打ち出しており、業界参入のハードルを下げる動きも出ています。 Aviation Wire
こうした点から、地上支援業務は「今、就職・転職先として狙うべき有望な領域」と言えるでしょう。
“退職代行から転職成功まで”のストーリー
事例A:20代女性・アパレル接客 → IT企業へ転職
- 大型商業施設でアルバイト・契約社員として勤務。
- 長時間のシフトやクレーム・上司の叱責により、精神的に限界を感じた。
- 直接辞める意思を伝えづらく、退職代行を利用。即日退職が成立。
- その後、転職準備に集中し、IT企業の事務職へ入社。ワークライフバランスは大きく改善。
事例B:30代男性・営業職 → 航空業界へ
- 月間ノルマ・深夜残業が常態化していた営業職。
- 上司との対立もあり、辞めたい意思を伝えられなかった。
- 退職代行を利用し、円滑に退職。
- その間に面接準備・自己分析を徹底。
- 安全が考慮されるため、勤務時間が厳格に管理されたグラハンへ転職成功。
- 家族で社員割引(EF)を使って、休みの日は家族で沖縄に。

退職代行は“選択肢”であり、転職成功への武器
本稿で示してきたように、退職代行は「逃げ道」ではなく、戦略的に使うべき 選択肢の一つ です。特に売り手市場の今、心身を守りながらキャリアを切り拓くためのツールになり得ます。
また、航空業界は、まさに需給ギャップが顕著な分野であり、未経験参入・キャリアアップの可能性を秘めています。待遇改善・DX導入・制度整備の流れも始まっており、将来的に有望な選択肢の一つと言えるとBeyond the Horizonでは考えています。そして航空業界は「ライフアンドワークバランス」重視される業界です。
「辞める勇気」は後ろ向きではなく、未来を切り拓くための 前向きな選択 です。
今がチャンスだからこそ、後悔しないキャリア選択を、冷静かつ戦略的に進めてほしいと思います。